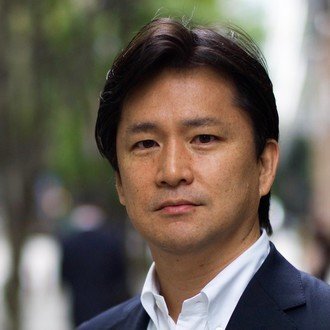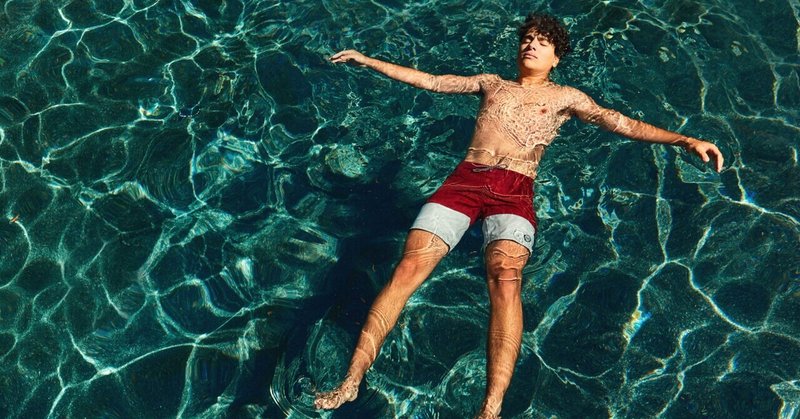記事一覧
「形から入る」ことも大切 ノー残業デーの設定から、数カ月後にベビーブームということもありました。
何かを大きく変えるとき、「形から入ること」も必要だと考えています。
こんなことがありました。
当時、わたしが働いていた会社では、残業が多く、ワークライフバランスの改善が必要という議論になっていました。しかし、おそらくマネジメントから現場まで、「ワークライフバランスなんか関係ない。結果を出すために働くんだ。」というのが本音だったのではないでしょうか。
そんななか、会社は行動しました。毎週水曜日
NASAの宇宙飛行士、スーパールームメイトを探している
スーパールームメイトという言葉を聞いたことがありますか?
連休の時間を使って、録画しておいたテレビ番組を観ました。
宇宙飛行士試験のドキュメンタリーです。
わたしは、宇宙飛行士には絶対になれませんが、一度くらい宇宙旅行をしてみたいものです。
さて、この番組のなかで印象的な話がありました。
NASAの宇宙飛行士選抜の考え方が変わってきているという話です。
昔は、宇宙飛行士になるのは「スー
元西武ライオンズ 辻さんのコメント 「これが野球」
3月10日から、ちょっとの期間日記を書くのをやめてました。深い意味はないですが、なんとなくそんな気分でした。
しかし、そう思った途端に、日記のテーマは現れるものです。
3月の大イベントと言えばWBCです。
在宅勤務の際には、Amazon Primeでの放映が頼りでした。家族は別のところでテレビを観ていて、わたしは机でAmazon Primeという日々でした。
Amazon Primeの映像は
「わたしが一緒に働きたい人」 たった1つの条件について考えてみました キーワードはTRUST
ふと、「わたしはどんな人と一緒に仕事しているときにHappyな気持ちになるのだろうか?」と考えるきっかけになった出来事がありました。
「Happyな気持ちになる」というのは、少し大げさな表現かもしれませんし、いい年のおじさんが、「Happy」とか言いながら働いているかと思うと、少し気持ちが悪いですね。
「Happyな気持ち」までいかなくても、余計なことを考えずに仕事に集中できることで十分でしょう
「優秀さ」と「率直さ」の使い方
昨年、ポールマッカートニーについてのnote.を書きました。
ポールは能力があり、実績も出しており、時には斬新な考えを提示し、良い作品を作るために(自己中心的なわがままも言ったのかもしれませんが)率直に自分の意見を言います。
こう書くと彼は何も悪くないように思うのですが、Get Backの中では、ポールの言動からジョージの脱退騒動にまで発展します。
では、ポールがジョージの意見を尊重し、少し
Aを優先してBを欠席するという判断について
このニュースで思い出したことがあります。
わたしが35歳くらいのときに、当時の上司が言っていた言葉が強く記憶に残っています。
「お客様とのミーティングを理由に、社内ミーティングを欠席するのは許さない」という言葉です。
正しいようで、実は必ずしも正しくないのは、「お客様など社外のミーティングは、社内ミーティングより優先される」ということです。わたし自身も、「社内の予定なので、そっちを調整します
そうは言っても、アグレッシブな法務やコンサバな営業じゃ困るでしょ という話
自分の性格と違う人を理解し、その違いを認めるというのは、意外と難しい話です。
あの人は末っ子だから、あの人はB型だから、あの人はxxだからという感じで、笑って済ませられるケースもあれば、仕事上の関わりとなると、そうも言っていられません。「あいつとは合わない」「あいつのことは理解できない」となったり、逆に意見の合う人だけで群れることもあるわけです。
この「性格」というのは、個人について存在する
「素人は戦略を語り、プロは兵站を語る」 セールス・キックオフの帰り道で見つけた言葉です
「素人は戦略を語り、プロは兵站を語る」
これは、第二次世界大戦時の米軍司令官 オマー・ブラッドリーの言葉だそうです。
兵站というのは、食料や兵器など、戦争に必要な物資を、戦いの最前線まで運ぶ経路を確保することかと思っていましたが、ネットで調べてみると、このような意味があるそうです。
この言葉を見つけたのは、セールス・キックオフの帰り道、オーランドの空港です。
わたしは、定期購読しながらも読ま
メンバーのモチベーションを気にしない?
Googleのオススメニュースによく出てくるのが、ダイヤモンド・オンラインの記事です。
いずれもタイトルが興味深く、ついついクリックしてしまいます。今日は、この記事を読みました。
わたしが28-35歳くらいまでは、この記事にあるようなことを考えてマネージャーとして仕事していました。この記事にある「仮面をかぶる」ことを意識して行動していたのです。
多分、わたしなりに色々な本を読んだり、自分の性
縄文時代の集落発展、6つのステージ 会社も同じだと思いました 函館旅行にて
年末年始は、函館にいました。何をしにいったということではないのですが、初めての函館でしたので、楽しい時間を過ごしました。
昨年夏、子どもと一緒に縄文時代の遺跡に始まり、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代を辿る旅をしました。
それ以来、少し縄文時代に関心を持っていたこともあり、函館駅に掲示されていたこのパネルが目に留まりました。
「縄文時代の集落展開と精神文化に関する6つのステー
監督を輩出できるチームについて
正月の風物詩、箱根駅伝です。
この時期になると、自分の出身大学を思い出します。一年前にこんなnote.を書きました。今年も大学のゼミメンバーのLINEグループで、ゼミ長が駅伝のニュースを投稿してくれました。
ことしは中央大学が大躍進しました。四年生の活躍もあったと同時に、一年から三年生までの活躍もあり、来年以降も楽しみです。
数年は厳しい期間がありましたが、躍進の要因には「規律」があったそうで
『ザ・ビートルズ Get Back: ルーフトップ・コンサート』のポール・マッカートニーとリーダーシップの難しさ
普段ディズニー作品を観ることはないのですが、Beatlesのこの動画を観たくて加入したDisney+でしたが、「観てよかった」と思える作品でした。
わたしなどは、ビートルズファンと言うのが憚られるくらいのレベルですが、昔飼っていたリクガメと犬の名前は、ジョンとポールでした。
娘の名前をリンゴにするのと、息子の名前をジョージにするのは家族の合意を得られなかったので実現することはありませんでした
滅びる民族三つの共通点というのがあって、どんな組織でも共通かもと感じた話
今週、知ったこと
イギリスの歴史学者、アーノルド・トインビーという人の言葉で、滅びる民族の「3つの共通点」というのがあるそうです。
滅びる民族の「3つの共通点」
Three common traits of a perishing people.
全ての価値を物やお金に置き換え、心の価値を見失った民族
理想を失ってしまった民族
自国の歴史を失った民族
なかでも、最も大事なのは三つ目だと